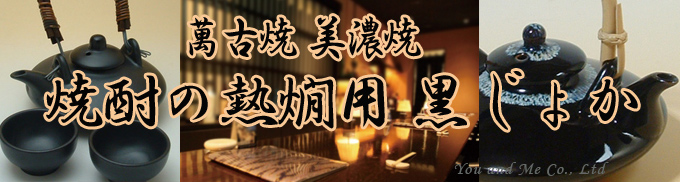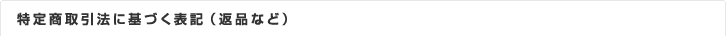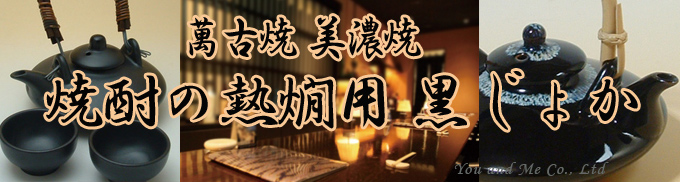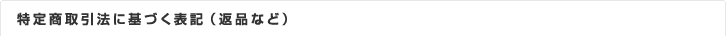薩摩発祥の焼酎専用酒器 黒じょかで差しつ差されつ 美濃焼の黒じょかとおそろいのおちょこ2個のセットです。 薩摩と言えば桜島と芋焼酎。 慶長年間(西暦1600年頃)藩主島津義弘光によって
朝鮮から招き入れた陶工により始められた薩摩焼がルーツの黒じょか。
17歳まで薩摩に居た篤姫は、果たして黒じょかで呑んだんでしょうか? 焼酎の一番美味しい呑み方は、やはり気の合う人と楽しく
飲み交わすのが最高の味と時間を生み出します。
◆優雅そして力強い、黒じょかの迫力と魅力
芋焼酎の伝統的な酒器黒じょか。
鹿児島の焼酎通に愛用されているこだわりの酒器です。
全体をかたどる独特の平らな曲線。鹿児島のシンボル桜島をかたどったと
言われる美しいフォルムです。職人の手で丁寧に仕上げられた黒じょかは、
細部にいたるまで美しさを表現しています。 末永く使っていただきたいと言う願い。使い込むうちに生まれる艶。
黒じょかが永く愛されている証なんです。 しかし今では黒じょかの職人さんの数が激減し、特に鹿児島産のものは
ほとんど手に入りません。 こちらの黒じょかも数少ない美濃焼の職人さんによって作られています。
◆黒じょかという名の由来
全部を漢字で書くと「黒直火」となります。
黒っぽい土瓶で直火にかけるから「黒直火」なんですが、
この黒じょかの由来は他にもいくつか存在します。 その一つなんですが、鹿児島では土瓶のことを「ちょか」と呼ぶそうです。
直に火にかけて使いますので、長年使い込むことで、
どんどん色が黒ずんでくる様子を含めて、この焼酎用の
土瓶だけを特に「黒直火」と呼ぶのではないかと思います。
黒い「ちょか」だから「黒ぢょか」と呼ぶとのことです。 また、「おちょこ」が「ちょか」になまったという説も。
この話題だけでも、黒じょかを眺めながら酒の肴になりそうですよね。
◆一番おいしい焼酎の楽しみ方
まずは焼酎をお好きな割合で水割りにし、2〜3日寝かせておきます。
酒たんぽややかんなどで熱めに温め、黒じょかに移して楽しんでください。
黒じょか自体陶器ですので、割れることはないと思いますが、
直火は不可とのことですので、火にかけないでください。
あとはおちょこに注いでチビチビとやってください。 水割りにする水と寝かせ方によって味が大きく変わり、
温かい「燗」にすることでその違いをさらに大きく感じられます。 サイズ:幅150×高さ83mm
容量:約430ml
重量:約430g
製造国:日本(美濃焼) |